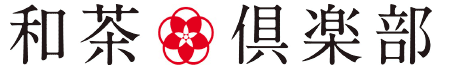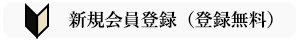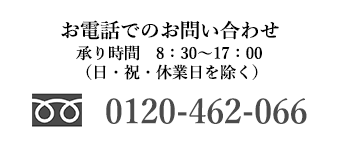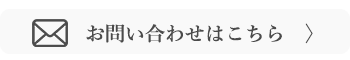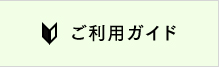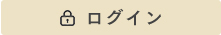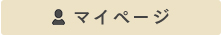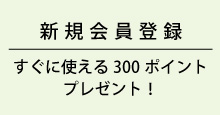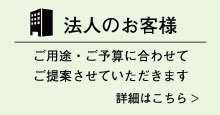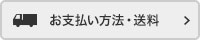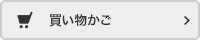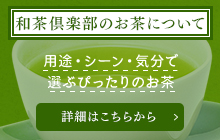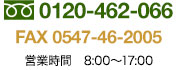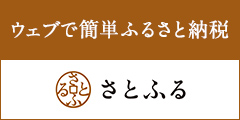廬山は中国を代表する観光地である。この茶は、漢代からあったとされる。
一芯一葉が基本で、清明節前後から摘み始める。
茶葉は、細く揉捻され、ツヤがあるのが特徴である。色は黒みをおびた緑。
爽やかで新鮮、濃い芳醇な味である。あと味も甘く、豆の香りがする。水色は、
透明感のある黄緑。
中国緑茶
- これより下にカテゴリはありません
廬山雲霧(ろざんうんむ)
六安瓜片(ろくあんかへん)
六安は地名、瓜片は茶葉が瓜の種に似ていることから名が付けられた。極品は「斉山名片」
ともいわれる。
芽は摘まず葉だけを穀雨前後に摘む。「名片」が一番茶で、「瓜片」はその次に摘む。
茶葉の特徴は、カールして揉んでいる。色は黒みをおびた緑で産毛がある。味は新鮮で、
あと味は甘い。清い香りは長く続き、水色は明るい黄緑である。
老竹大方(ろうちくだいほう)
老竹峰のある茶区で最初につくられたので名付けられた。大方は作った僧の名である。
このお茶の最上のものを「頂谷大方」という。
「頂谷」は雨前に一芯二葉で摘み、「老竹」は穀雨から立夏にかけて一芯二葉または
一芯三葉で摘む。
茶葉は黒みをおびた緑色で、味は芳醇でボディがある。香りは高く栗の香りがする。
水色は、透明感のある薄い黄緑。香りの吸収力が強く、花茶のベースにも使われる。
臨海蟠毫(りんかいはんごう)
漢の時代、杭州地域は茶区があったといわれ、明代にはたくさん生産されていた。
一芯一葉または一芯二葉で、清明節の前後2週間位で摘まれる。とぐろを巻くような
状態(蟠)に揉捻され、銀毫があるところからこの名前が付けられた。
茶葉は、シルバーグリーン。芳醇でまろやかな味で、香りが高く新鮮である。水色は、
薄く上品な黄緑。
龍山雲毫(りゅうざんうんごう)
龍山茶園で採れ、産毛があるのでこの名前になった。
一芯一葉または一芯二葉で、2月上旬から11月下旬までの長い期間摘めるお茶である。
茶葉の特徴は、産毛があり、細く強く揉捻されている。色は黒みをおびた緑色。
香りが高く、栗の香りとも例えられる。味は新鮮で爽やか、あと味も甘い。水色は、
透明感のある黄緑である。
龍岩斜背茶(りゅうがんしゃはいちゃ)
龍岩市の斜背村で産するので、この名前が付けられた。斜背村は300年以上の製茶の歴史が
ある。
立夏前後に摘む。茶葉は暗い黄緑色をしており、水色は赤みおびた黄色である。
濃くボディがある味で、中国産オリーブのようなあと味がある。香りも独特である。
蘭渓毛峰(らんけいもうほう)
1972年に作られた新しい銘茶である。良い茶葉は、茉莉花茶のベースにもなる。
一芯一葉または一芯二葉で、清明節前後、10日から2週間程度で摘む。
茶葉は細く、産毛がる。芳醇で爽やか、甘い味が特徴である。清香系の澄んだ香りは
長く続き、水色は薄い黄緑。
涌渓火青(ゆうけいかせい)
涌渓とは地名で、作り方は屯緑などから吸収していた。
一芯二葉で、清明節から穀雨の間で摘む。顆粒状に揉捻され、重い感じがする。
茶葉の色は、黒みがかった緑である。味は、ボディがあり芳醇。あと味も甘い。
花の香りが特徴的で長く続く。水色は、柔らかで薄い黄緑。
蒙頂甘露(もうちょうかんろ)
2000年以上前の漢代からあるお茶である。蒙山の頂に茶木が植えられていて、お茶の味は
甘い露のようなので、この名が付けられた。唐代から清代まで献上茶であった。
一芯または一芯一葉で春分のころから柔らかいものだけを摘む。
茶葉はしっかり揉まれ、白毫が多く、柔らかな緑色である。味は新鮮で爽やか、あと味が甘い。
水色は、透明な緑で少し黄色がかっている。
望府銀毫(ぼうふぎんごう)
望府山(望府楼)で産するお茶なのでこの名称となった。
一芯一葉が基本で、春分前後に新芽を他より早く摘む。茶葉の特徴は、太くまっすぐで、
産毛があり、白みをおびた緑色で光沢がある。味は新鮮で芳醇、さらりとしてあと味が甘い。
香りは、純で素直な感じである。水色は、透明感のある薄い黄緑。