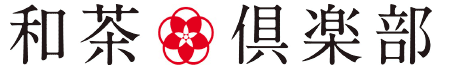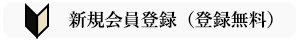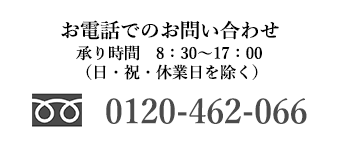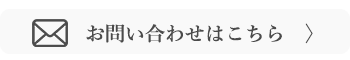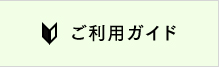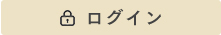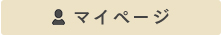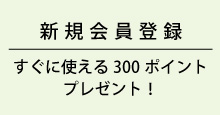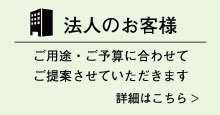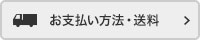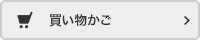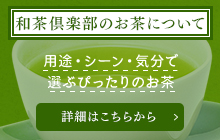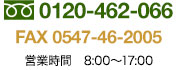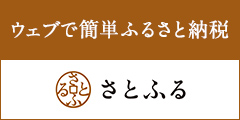東シナ海を望む天台山脈に連なる望海崗で作られたことからこの名がついた。
一芯一葉が基本で、穀雨前後で摘む。茶葉は、細く真っ直ぐで、深く黒い緑色。味は芳醇で、
あと味が甘い。香りは栗の香りがし、長く続く。水色は、柔らかなごく薄い緑である。
中国緑茶(2ページ)
- これより下にカテゴリはありません
望海茶(ぼうかいちゃ)
平水珠茶(へいすいじゅちゃ)
平水は、茶の集積地で、唐代からの茶の交易地でもあった。
揉捻が独特で、強く丸く珠状にする。国外では形からGun Pow-der(火薬)の通称で呼ばれた。
形状が緑の真珠にも例えられGreen Pearlとも呼ばれた。
丸まった茶葉は、ツヤがあり、脂っぽい感じがする。水色は黄金色である。
普陀佛茶(ふだぶっちゃ)
普陀山で産することからこの名になり、普陀山は中国の仏教四大名刹の一つである。
日本の煎茶普及のきっかけを作った隠元も、この寺で修行をした。
一芯一葉または一芯二葉で、清明節の3~4日後に摘む。茶葉の特徴は、白毫があり
黒みがかった緑色。水色は淡い黄緑。
日本の煎茶の味、香りに共通性がある。
磐安雲峰(ばんあんうんぽう)
磐安は「茶経」にでてくる東白茶の茶区の一つである。
4月下旬から5月初めにかけて、一芯一葉または二葉で摘む。芽は肉厚である。
「三緑一香」と呼ばれる。三緑は、茶葉の色・水色・お茶をだしたあとの茶葉の色のこと。
一香は、菊の花の香りを指している。
白雲毛峰(はくうんもうほう)
1950年代以降に白雲山で作られたお茶である。
一芯一葉または一芯二葉で、穀雨前後に摘む。
茶葉は、細く産毛があり、色は黒みをおびた緑色である。味は、新鮮で芳醇である。
あと味は甘く、柔らかな香りは長く続く。水色は透明で薄い黄緑。
南京雨花茶(ナンキンうかちゃ)
1950年代後半に作られ南京の雨花台にちなんで名づけられた。
基本的に一芯一葉で清明節の前後に摘まれる。
茶葉は、針のように細く揉まれ、尖っているのが特徴である。味は新鮮で芳醇。
香りは上品で濃い。水色は透明感のある黄緑である。
屯緑(とんりょく)
現在の黄山市周辺で作られたお茶。屯渓緑茶の略である。
茶葉は細く尖り、黒みがかった緑色でツヤがある。あと味が甘く、栗の香りが特徴。
水色は黄緑である。
東白春芽(とうはくしゅんが)
東白山で産するので、この名がつけられた。
一芯一葉または一芯二葉で清明節から穀雨の間に摘む。
茶葉の特徴は、産毛があり白みがかった緑色で、蘭の花に似ている。
味・香りは、芳醇で新鮮、栗の香りや蘭の香りにたとえられる。水色は澄んだ黄緑。
東山碧螺春(とうざんへきらしゅん)
太湖の東洞庭山で摘まれるものが最上とされる。茶畑ではなく、梅、桃、柿、杏などの
果物畑で、果樹の下に茶木が植えられている。
100gに8千~1万5千の茶葉があるといわれ、細かくタニシのように曲がっていることから、
この名になった。
基本は一芯一葉で、春分から穀雨までに摘み、明前が最上とされる。
東海龍舌(とうかいりゅうぜつ)
東シナ海の側に植えられており、葉の形が龍の舌ににていることから名づけられた。
一芯一葉あるいは一芯二葉で摘まれる。上質のものは、芽だけで作るものもある。
茶葉は、細長くツヤがあり黒みをおびた緑色をしている。味はさらりとし、芳醇。
香りは長続きする。水色は、明るく透明感がある。