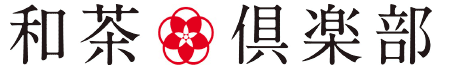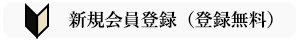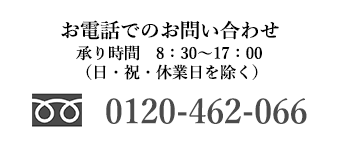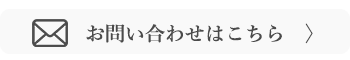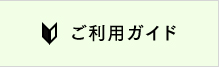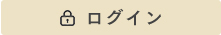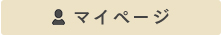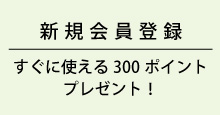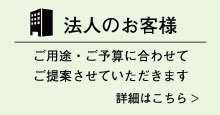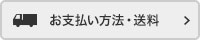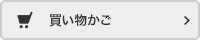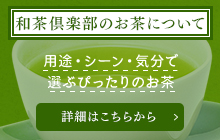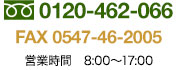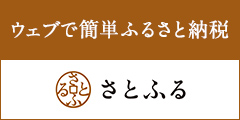金山という場所で産することから名付けられ、新しい銘茶である。
穀雨前後に一芯一葉の開くか開かないかの状態で摘み、3時間ほど発酵させた
のち高温で殺青する。
葉は細長く、産毛があり深い緑色。香りは柔らかく、味は芳醇。
水色は、明るい柔らかな黄緑で、出したあとの葉も緑色である。
中国緑茶(6ページ)
- これより下にカテゴリはありません
金山翠芽(きんざんすいが)
峡州碧峰(きょうしゅうへきほう)
上質の茶葉は、一芯一葉で摘まれ、一芯二葉となると等級が下がる。
葉は細長く、ツヤがあり深緑色である。
味・香りは、清く高く香り、長く続き、あと味が甘く芳醇である。
水色は、明るい山吹色で、出したあとの茶葉も柔らかな緑色をしている。
休寧松蘿(きゅうねいしょうら)
松蘿山は黄山の南麓で産するので名づけられた。
基本的に一芯二葉または、一芯三葉で穀雨の前後に摘む。
炒るときに、釜の横で一人が扇子で風を送り、熱気をとばして、黄色にならない
ようにする工程が特徴である。
茶葉は、ツヤのある緑で柔らかな中国産オリーブのような香りがし、味は濃い。
鳩抗毛尖(きゅうこうもうせん)
千鳥湖の湖畔の淳安県鳩抗郷で産するのでこの名がつけられた。
明前に一芯一葉を基本に摘み、板の上で両手で柔らかく揉む。
葉は深緑で、まっすぐである。水色は透明感があり、柔らかな黄色。
味・香りは、濃く、清らかで長続きする。
官庄毛尖(かんしょうもうせん)
強い揉捻で細く仕上げている。
飲んだあと、爽やかで香りが長く続くのが特徴であり、水色は緑がかかった
山吹色。茶葉の色は深い緑色をしている。
峨眉竹葉青(がびちくようせい)
竹の葉に似た青みのある茶葉であることから名付けられた。
水色は、明るく、清い黄緑色。
一芯一葉または、一芯二葉で摘み、茶葉の大きさがそろっているのが特徴であ
る。爽やかで、味は濃く、芳醇。
峨眉峨蕊(がびがずい)
古くからの銘茶の産地である峨眉山で採れ、花の芯のような形をしており、
峨蕊と名づけられた。白芽、雲芽、雪芽などともいわれていた。
芽だけを摘んだのちすぐに製茶する。炒り、揉捻を数回行う。
鳩抗毛尖(きゅうこうもうせん)
葉は深い緑で白毫があり、水色は透明感のある、やわらかな黄色。香りは、清らかで長続きし、味は濃く、ポディがある、しかもさわやか。また、揉捻に特徴があり、板の上で両手で優しく揉む。
淳安県鳩抗郷で生産されることでこの名がついたこのお茶は、唐の頃、主要銘茶として扱われていた。
休寧松籮(きゅうねいしょうら)
松籮山で生産されるこのお茶は、唐代から生産されており、明代から特に名が広がっていった。
茶葉は緑色で艶があり、中国産オリーブのような柔らかな香りをしている。味はポディがあり、濃い。またこのお茶は「三重」と呼ばれ、色濃く、香り濃く、味も濃いことからきている。
このお茶は炒るとき、釜の横で扇子を使い風を送り、茶葉が黄色にならないように、熱気を飛ばす工程は特徴である。
峡州碧峰(きょうしゅうへきほう)
この茶葉は細長く、艶のある深い緑色をしている。香りは、清く高く香り、長時間続く。後味が甘く、水色は明るい山吹色をしている。出した後の茶葉もやわらかな緑色をしている。
一芯一葉で摘まれるものは上質の茶葉で、一芯二葉となると等級が下がる。