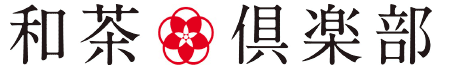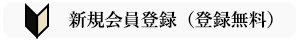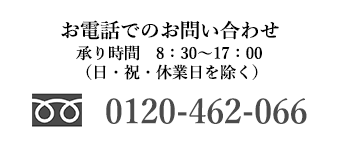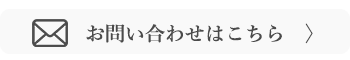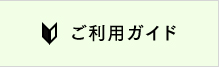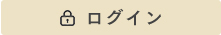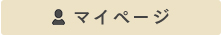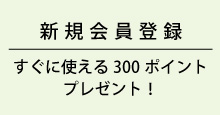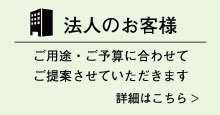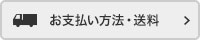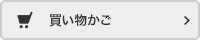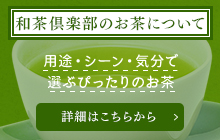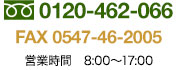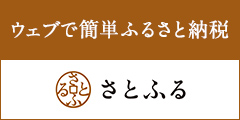日本の茶産地では、九州、四国、東海地方の平坦地では最大年三回程度、多い所では四回もの摘採ができるが、北限付近や温暖地域でも標高の高い山間地などでは年二回の摘採にとどめている。近年は生産コストと市場価格の低下から温暖地域でも二回の摘採にとどめる傾向にある。覆下園の玉露やテン茶の原料については年一回の摘採に止めている。一年の中で第一回目の摘採を一番茶と称し、以下、二番茶、三番茶・・・と称している。
摘採開始の樹齢
一般的には、二年生苗を定植してから三年目からはじめて摘採できる。ちなみに、実生園ではあるが、陸羽の『茶経』にも三年目から摘むとされている。
二番茶以降の整枝
三番茶まで摘採する温暖地では、二番茶摘採後も一〜二回の整枝を行う。四番茶まで摘採する場所では、三番茶摘採後にもやはり整枝を行う。二番茶までしか摘採しない場合は二番茶摘採後生育を放任すると、秋末までにかなり過剰に繁茂するので、二番茶摘採後二〇日目頃に遅れ芽を除去しておくと良い。この処理が行われなかった場合、十月下旬〜十一月上旬になってから、翌年の一番茶摘採予定面上に一〇〜一五センチの葉層を残して、その上方の過剰な繁茂部分を除去すると、越冬中の被害を軽減・防止することができる。
一番茶後の整枝
一般的に整枝は成園で、最終摘採面から二〜三センチで刈る。一番茶の摘採が終わったら、その摘採面にそって遅れ芽を除去するが、その実施時期は静岡で摘採後一〇〜一四日目に一回、鹿児島では五日後と二〇〜二二日後と二回行われている。
整枝による芽数への影響
深めに整枝すると芽数が増すが、個々の芽は小さめとなり、浅く整枝すると芽数は少なくなる一方で、芽は大きく育って『芽重型』となる。近年はこの芽重型の仕立て傾向が強い。
春整枝
北限地付近や山間地で標高が高いため、冬期に寒害を受ける恐れが大きい場所では越冬後の二〜三月になって春整枝を行う。
秋整枝
秋整枝は、時期が早過ぎると整枝後にまた萌芽して生育してしまい、遅過ぎると翌年の一番茶摘採が遅れる。整枝の目安は日の平均気温が十五〜十八度程度より低めが良く、再萌芽しなくなるのを目安に実施する。例として、静岡では十月上〜中旬、南九州では十月上〜下旬が実施適期とされている。温暖地では春整枝に比べて、秋整枝をしておいたほうが萌芽が揃い、萌芽期や摘採期が早まる。
整枝
一般の機械摘み茶園では各茶期の前に、摘採面の凹凸をならし揃えて、次の茶期の摘採を行う際に、摘み取られる新芽の中に古葉や枝、前茶期の摘採後の遅れ芽の硬化したものなどが混じって、茶の品質低下をさせないよう、浅い刈り払いを『整枝』(株ならし)という。秋に行う整枝を秋整枝、春に行う整枝を春整枝という。
幼木期間の管理
幼木は樹体も小さく、葉数も少ないため各種の抵抗性も成木に比べて弱い。保護管理の良否は成園化の遅速にも影響する。越冬時の保護や少雨期の土壌水分減の防止(潅水・マルチ)、各種病害虫の防除、除草、過度の摘採の抑制などが必要。植え付けてから成園になるまでの年数は暖地、北限地などの地方によって異なる。
幼木の仕立て方
幼木期に主幹の徒長を抑えて分枝数を多くし、とくに側方の枝の成長を促して、株ばりを良くするとともに、できるだけ生育が良く、かつ均整な枝を摘採面上に数も過不足なく作り上げより早期に生産性の高い樹体にする。
定植時は一五〜二〇センチ程度、二年目の一番茶前期には二〇〜二五センチ、三年目一番茶期前には三〇〜三五センチ、三年目秋か四年目の春整枝時には四〇〜四五センチ、五年目には四〇〜四五センチ程度と毎年五〜六センチ程度の高さでで揃えていく。